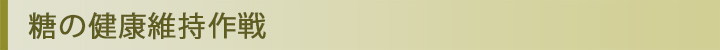めまいと糖
生活習慣の乱れは、自分でそれと気づかないうちにトラブルを抱えてしまう場合が多々あります。
トイレが近いとか、尿が泡立っているなどは、最近では比較的よく知られるようになりました。
しかし、ちょっとした立ちくらみやめまいなどは、ほとんどの人が軽く考えて、気にしない場合が多いようです。
じつは、こうしためまいや立ちくらみというのは、大きく以下の3つの原因が考えられます。
1)脳の血流に問題がある場合
2)耳の奥にある「内耳」に問題がある場合
3)自律神経に問題がある場合
糖の健康を維持できない状態が続くと、ソルビトールと呼ばれる物質が大量に産生され、蓄積されて、上記3)を引き起こすことになるのです。
自律神経というのは、心拍や血圧、その他すべての臓器の働きを、その人の心身の変化に応じて、本人が安全で快適にいられるよう、プラスとマイナスの働きでバランスをとりながら絶えずコントロールしてくれる神経です。
ですから、自律神経障害におちいると、全身の機能に影響を及ぼし、様々なトラブルが発生することは容易にご理解いただけることでしょう。
そのトラブルの1つが、めまいや立ちくらみというわけです。急に立ち上がったときや入浴時に血管が広がったときなどに血圧がうまくついていけず、こうした症状が起こってしまいます。
また、糖の健康を維持できないと血流が悪くなるので、内耳のバランス感覚を司る器官(三半規管)やその周辺に充分な栄養が届かないことでめまいを起こす場合もあります。
そうした場合、そもそも一般的なめまいと違って、糖のトラブルが大きな原因となっていますので、糖が安定しないかぎり解決は難しく、不快感は悪化の一途をたどってしまうことになります。
最初はめまいや立ちくらみ程度でも、手足の感覚や力の入れ具合が分からなくなったり、障害物がなくてもすぐにつまづいたり、階段の昇り降りや車の運転も難しくなるかもしれません。
そのほか、じつは薬の副作用でめまいが起こることもあります。
天然のものと違って、一方的な働きしかもたない化学薬剤は、環境や体調の変化によって上下する体内成分の濃度にうまく対応することができません。
したがって、運動で急に代謝が高まった時などは、薬剤の効果が過剰になり、めまいや意識の低下が起こり得ます。
つまり、糖の健康を維持できないと、めまいを起こしやすくなるということを認識しなければならないのです。
アミノ酸サプリメントは要注意!
2015年1月末、東京大学の研究チームが以下の研究結果を「米国科学アカデミー紀要」(PNAS)に発表しました。
研究チームは、2型糖尿病患者の一部で血液中のL-システインが長期的に増えることに着目し、マウスのβ細胞を使って実験を行い、血液中のL-システインが増えるとβ―細胞からのインスリン分泌が抑制されることを明らかにしています。
この実験では、L-システインを取り除くと、インスリン分泌は1時間半程で回復したとしています。
つまり、L-システインはインスリン分泌を調節している新たな制御因子である可能性があるということです。
L-システインは、アミノ酸サプリメントとして幅広く飲用されていますが、糖の悩みをもつ人が利用すると悪化につながるため、サプリメントや健康食品にどのような成分が含まれるか、よく確かめるよう警告しています。
「テトウストレ」は天然のハーブであり、医薬品ではありません。